◇◆注意事項◆◇
これからご紹介する内容は、50代のA夫さんの体験談です。わからないことはその都度、弁護士の先生や家庭裁判所に確認しながら進めたとのこと。相続財産の内容や相続人の状況は千差万別ですので、あくまでも参考程度にとどめ、相続・相続放棄については必ず専門家へご相談ください。
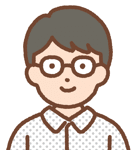
こんにちは。A夫です。
借金発覚から相続放棄までの体験談をご紹介します。
借金の発覚
一人暮らしをしていた父が亡くなり、遺品整理をしていたところ怪しいものが出てきました。銀行口座から毎月決まった相手への振込、ATMからの頻繁な出金、未使用の現金書留袋…。嫌な予感がして銀行に過去10年分の履歴を請求し、借用書や督促状がないか徹底的に確認しました。
結果、金融機関からの借金はなかったものの、親戚や知人から150万円以上の借金があるらしいことが判明しました。
借金の総額がわからない
父は年金暮らしでした。日々の生活は特に困った様子はなく、孫の誕生日にはプレゼントをくれる良いおじいちゃんでした。しかし、20年前の事業不振であちこちからお金を借りていたようです。
借用書も返済記録もなく、誰からいくら借りているのか不明。古いメモや現金書留の封筒は見つかるものの、返済が終わっているかもわからず、連絡先すら不明でした。
相続放棄という選択
相続状況を整理すると、預貯金は30万円程度、価値のないコインや切手が多数、一方で借金は不明ながら150万円以上。プラスよりマイナスが多い可能性が高く、相続することが怖くなり「相続放棄」という選択肢が浮上しました。
法律事務所へ相談
亡くなってから1か月半後、法律事務所へ相談。
弁護士から「相続を知ってから3か月以内なら相続放棄が可能」と説明を受けました。その際強調されたのは「遺品や預金を勝手に処分していないか」という点。
もし現金を引き出したり遺品を売却していれば、相続放棄は認められないとのことでした。幸い何も手をつけていなかったので、放棄可能と判断されました。
相続放棄の手続き
弁護士から「手続き自体は難しくない」と勧められ、自分で行うことに。流れは以下の通りです。
- 必要書類の準備(戸籍・除票など)
- 申述書の作成(家庭裁判所HPから入手可)
- 家庭裁判所へ提出(収入印紙・切手が必要)
- 家庭裁判所からの確認書類に回答
- 相続放棄申述受理通知書を受領
実際やってみると、なんとかできました。わからないことはネット検索したり、市の無料法律相談に聞いたりして解決しました。
申述書の提出後10日ほどで確認の郵便が届き、返送すると「相続放棄申述受理通知書」が届きました。これで手続き完了です。これをもらった時は心底ホッとしました。
次順位の人への連絡
相続を放棄すると、相続権は次順位の人に移ります。
我が家の場合は父の兄弟と代襲相続となる従姉です。特に知らせる必要はないのですが、今後の付き合いを考え、法要の際や電話・手紙で説明を行いました。最初は驚かれましたが、丁寧に説明を重ねた結果、相続放棄に理解を頂き、皆さんも相続放棄を選びました。
これでようやく父の借金が終わりとなりました。
まとめ
今回、父の遺産は実質的に借金ばかりで、手続きが面倒な不動産相続もなかったので相続放棄という選択をしました。
手続き自体は戸籍や申述書の準備など地道な作業ですが、弁護士や家庭裁判所に相談しながら進めれば難しくはありません。
大切なのは「財産に手をつけないこと」と「期限を守ること」。
相続は遺産所状況や相続人の人数、関係性などによって変化しますので、ネット検索ばかりに頼って判断するのは危険です。専門家に相談することを強くおすすめします。
私の体験談は以上となりますが、同じような状況に直面した方の参考になれば幸いです。


