親が亡くなった直後は、深い悲しみの中でも多くの判断と行動が求められます。何から手をつけていいか分からなくなることも少なくありません。ここでは、葬儀までに必要な大まかな流れを、チェックリストと時系列で整理しました。
【親が亡くなったらすることチェックリスト】
□ 医師による死亡確認を受け、死亡診断書を受け取ったか(コピーも数部用意)
□ 葬儀社へ連絡し、遺体の搬送先を決めたか(自宅 or 安置施設)
□ 役所で火葬許可証を取得したか(葬儀社に代行を依頼する場合も)
□ 僧侶・式場・火葬場と調整し、葬儀の日程・内容を確定したか
□ 親族・関係者へ訃報連絡を行ったか(危篤時に連絡していない人へも)
□ 勤務先や学校へ休暇・欠席の連絡をしたか(必要なら引き継ぎも)
□ 葬儀費用の支払い方法を確認したか(現金・振込・クレジットなど)
□ 僧侶へのお布施や戒名料の準備をしたか(現金が望ましい)
□ 預金口座の凍結を考慮し、必要なら金融機関に確認したか
□ 通夜・告別式・火葬へ向けて当日の流れや役割分担を確認したか
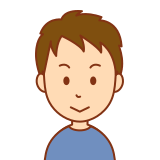
それでは具体的にどんなことをするか確認です
医師による死亡確認と死亡診断書の受け取り
まず必要なのは、医師による死亡確認です。病院・自宅・施設など、亡くなった場所によって対応が少しずつ異なりますが、医師による確認を経て死亡診断書を受け取ります。
死亡診断書は葬儀や火葬の手続きに必要なだけでなく、相続手続きでも必要になりますのでコピーを数部とっておくと良いでしょう。
葬儀社へ連絡し、遺体を搬送
病院に遺体をずっと安置しておくことはできません。葬儀社が決まっていればすぐに連絡を。
まだ決まっていない場合は、この時点で選びます。
搬送先は自宅か葬儀会社の安置施設となりますが、葬儀までの日数が長いと保管料やドライアイス代が追加でかかる場合があります。また搬送が深夜になる場合は深夜料金が発生することもあります。
役所で火葬許可証を取得
火葬には役所が発行する火葬許可証が必要です。葬儀社が代行してくれることが多いですが、申請期限があるため早めに対応します。
葬儀の日程・内容の最終決定と訃報連絡
葬儀の日程や内容は、僧侶・式場・火葬場などの空き状況を確認しながら決定します。併せて参列者の範囲や葬儀の規模も最終確定させましょう。
日程が決まったら、参列者への連絡と、危篤時に連絡していなかった親族や関係者へ訃報を伝えます。
連絡は電話が基本ですが、遠方や連絡がつきにくい場合はメールやメッセージも併用すると良いでしょう。
職場・学校などへの連絡
勤務先や学校に訃報を伝え、休暇や欠席の連絡をします。必要であれば業務の引き継ぎも行います。
葬儀費用と支払いの準備
葬儀費用は現金払いが多いですが、振込やクレジットカード対応の葬儀社も増えています。
僧侶を呼ぶ場合のお布施や戒名料は別途必要で、全国平均は15〜200万円と幅広く、現金で用意します。
銀行口座は名義人死亡で原則凍結されますが、金融機関によっては葬儀費用のみ相続手続き前に払出し可能な場合もありますので必要であれば事前に確認しておきましょう。
通夜・告別式・火葬へ
日程に沿って通夜や告別式を行い、火葬を終えます。当日は弔問客の対応や進行が続きますが、事前準備が整っていれば落ち着いて臨めます。


