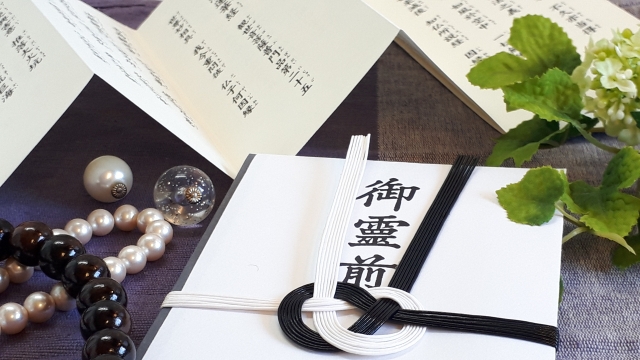葬儀は突然やってくることが多く、準備が不十分なまま本番を迎えて慌ててしまうことも少なくありません。大きな流れや手続きは葬儀会社がサポートしてくれますが、実際に経験した人の声から「これをやっておけばよかった」という小さな工夫もたくさんあります。ここでは、通常のチェックリストには載っていないけれど、葬儀をスムーズに進めるための“ちょっとしたコツ”をご紹介します。
葬儀会社とタッグを組む
50代の私達世代では、葬儀の喪主を務めるのは初めてという人が多く、不安や疑問は尽きないものです。
そんな時に心強いのが葬儀会社です。「病院からの遺体搬送はどうする?」「お布施の相場は?」「火葬後に会食は必要?」など、わからないことは遠慮せずに相談してみましょう。葬儀会社はプロとして適切にアドバイスしてくれます。
一方で、深夜の搬送など追加料金が発生する場面もありますが、それは正当な費用として受け止めることが大切です。葬儀会社とお互いに信頼関係を築き、タッグを組むことで、葬儀をより安心して進めることができます。
喪主挨拶はAIを利用する
葬儀会社によっては、喪主挨拶の文例を用意してくれることもあります。しかし、その用意がない場合もあり、式の流れの中で「喪主様、ご挨拶を」と突然促され、言葉に詰まってしまう人も少なくありません。
最近ではAI、特に文章作成能力が高く無料で利用できるChatGPTなどを使って、喪主の挨拶を事前に作っておく人も増えています。
コツは「長すぎず」「感謝の気持ちを中心に」「故人らしさをひとこと添える」こと。家族葬など小規模な式でも、準備しておくと心強いものです。
例えば、ChatGPTに「家族葬の喪主挨拶を作成して欲しい」と入力するだけで、こんな内容が返ってきます。
「本日はお忙しい中、〇〇(故人の名前)のためにお集まりいただき、誠にありがとうございます。
生前は皆さまに大変お世話になり、家族一同、心より感謝申し上げます。本日は近親者のみでのささやかな家族葬とさせていただきました。故人も静かに見守ってくれていることと思います。
今後も私たち家族で力を合わせ・・・・、 以下略。
どうでしょうか?
ここから更に家族での思い出や個人の希望などを盛り込んでカスタマイズしていけば あなただけの喪主の挨拶になります。
葬儀はやること、決めることが多いです。喪主の労力が少しでも省けるなら省いていきましょう。
手書きでいいから「親族一覧図」を作る
普段は「大阪のおじさん」「ケイコおばさん」等と呼んでいて正式な続柄が分からない、名前がわからないということがあります。
このままの状態で葬儀を迎えると「この人誰だっけ?」と戸惑うことがあります。特に配偶者や子どもが対応する場合、「誰とどういう関係か」が分からないと困る場面も。
そこでおすすめなのが、手書きで構わないので簡単な家系図や親族一覧を作っておくこと。誰がどの立場で、どんな呼び方をしているのかを整理しておくだけで、親族間のやりとりがスムーズになります。
出欠と香典を記録しておく
通夜・告別式・火葬・会食など、誰がどこまで出席するのかを記録しておくと便利です。さらに、香典額も控えておくと、後日の香典返しの手配がスムーズになります。
この一覧は四十九日や一周忌など法要の出欠、将来ほかの親族の葬儀に参列する際の参考にも役立ちます。「自分は行くべきか?」「配偶者や子どもも一緒に出るべきか?」「香典はいくらにすべきか?」と迷ったときの判断材料になるのです。
その他のちょっとした工夫
- 弔電や供花の送り主の控え:当日は慌ただしいため、誰から届いたか記録しておくと後日の御礼がスムーズです。
- 写真を残しておく:不謹慎と思われるかもしれませんが、祭壇や供花の様子などを参列者が来てない時間帯に写真(画像)に残しておきましょう。今後の参考となるはずです。葬儀会社が記録撮影してくれる場合もあります。
- 筆記用具や封筒の予備:香典袋の記入や急な連絡先のメモに役立ちます。
- 服装小物の確認:黒の靴下やストッキングなどは意外と忘れがち。予備を用意しておくと安心です。
まとめ
葬儀は大きな行事ですが、意外と「ちょっとした準備」が当日の安心感につながります。喪主挨拶や親族図、香典の記録などはどれも簡単にできることですが、やっておくと想像以上に役立ちます。悲しみの中で慌てずに対応するために、ぜひ取り入れてみてください。