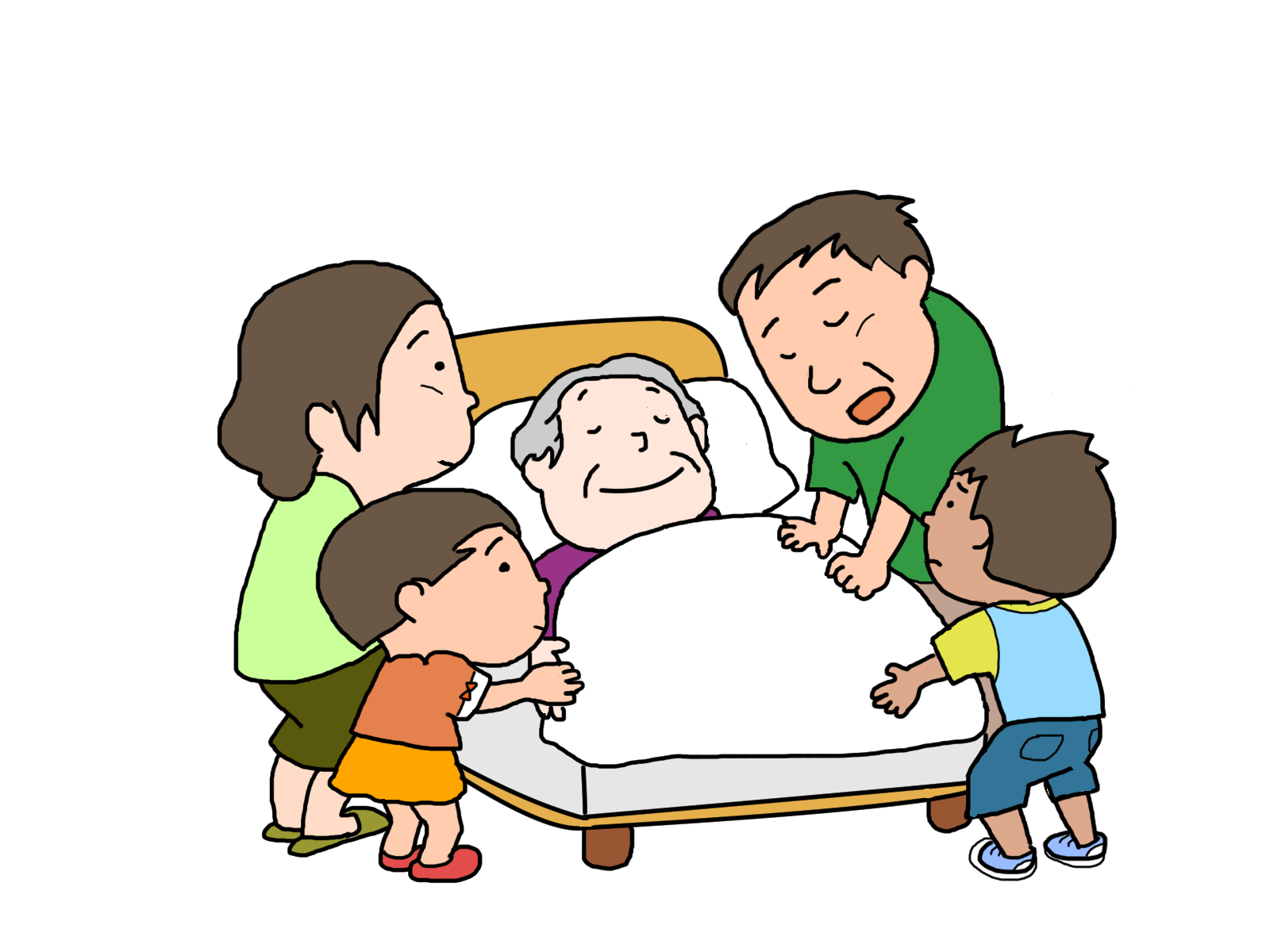「お父さん(お母さん)の容体が急変しました」
50代にもなると、いつそんな連絡が来てもおかしくありません。
葬儀関係は全て親に任せてきた人も多いと思いますが、今度は自分達が葬儀を執り行う番です。
この記事では、初めて近親者の葬儀を経験する人向けに、簡単な葬儀の基礎知識と、最初にとるべき行動を解説します。
【知識①】亡くなる場所によって変わる「最初の対応」
病院で亡くなる場合
- 医師が死亡確認を行い、死亡診断書を発行
- 病院から葬儀社を紹介されることがありますが、選択は完全に自由。紹介を断って自分で選んだ葬儀社を呼んでも問題ありません
- 事前に候補を決めておくと、いざという時に困りません
自宅で亡くなる場合
- 医師による死亡確認が必須
- かかりつけ医がいない場合、警察が来て「異常死扱い(検案)」となり、所要時間が長くなることがあります
- その後に葬儀社による搬送。この場合も事前に葬儀会社を決めておくと搬送もスムーズです。
介護施設で亡くなる場合
- 医師(または嘱託医)が死亡確認
- 施設によっては契約葬儀社が指定されていることもありますが、これも変更可能です
【知識②】お葬式の一般的な流れ
地域、宗派等によって異なりますが一般的な例として紹介します。
- 通夜 → 告別式 → 火葬が一般的
- 地域によっては順序や名称が異なる場合もあり
- 納骨や四十九日法要は、火葬直後に行う場合もあれば、自宅安置後に四十九日まで保管する場合もあります。※
- 最近は一日葬(通夜を省き、告別式と火葬を同日に行う)も増加傾向
※納骨は、四十九日法要と同時、または一周忌など大きな法要の節目に合わせて納骨するのが一般的ですが、必ずしもその時期でなければならない決まりはなく、遺族の都合や心情に合わせて選んで構いません。
【知識③】主な葬儀スタイル
葬儀は、規模や進め方によって大きく3つのタイプに分けられます。
それぞれ費用や遺族の負担度が異なるため、事前にどの形式にするかを検討しておくことが大切です。
| 葬儀スタイル | 特徴 | 参列者数の目安 | 費用の目安(全国平均) |
|---|---|---|---|
| 一般葬 | 多くの参列者を招く伝統的形式 | 50〜200人程度 | 100〜200万円前後 |
| 家族葬 | 親族中心、小〜中規模まで幅広い | 10〜30人程度 | 50〜150万円前後 |
| 直葬(火葬式) | 通夜・告別式を省き火葬のみ | 2〜10人程度 | 10〜50万円前後 |
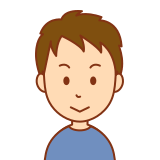
それでは大体の基礎知識を頭に入れたら、
次は実際の行動へと移りましょう。
葬儀スタイルは最初に決めておく
危篤時には、できるだけ早い段階で葬儀スタイルを決めておくことをおすすめします。
一般葬、家族葬、直葬(火葬式)など形態によって、危篤時に誰へ連絡するかが変わり、連絡の手間や負担も大きく異なります。
また、事前に方針を固めておくことで、葬儀会社との打ち合わせ中に規模が膨らんで費用が増える事態を防ぐことができます。
さらに、親戚から「葬儀はどうするのか」といった問い合わせがあっても、決まった方針に沿ってスムーズに答えられます。スタイルが明確なら、関係者の理解も得やすく、当日の準備や進行も円滑に進みます。
親戚への連絡
職場への連絡と準備
「そろそかもしれません・・・」と医師から言われたら、職場へ連絡を入れておきましょう。
忌引きが必要になること、業務の引き継ぎ、いつからいつまで休むかなどの連絡は必須です。
- 忌引き日数を確認(勤務先によっては配偶者の親でも取れる場合もある)
- 業務の引き継ぎメモを簡単に作っておく
- 葬儀日程は未定でも「亡くなるかもしれない」ということを連絡しておく
葬儀会社を決める
葬儀は時間との勝負になることが多く、葬儀会社の選定は事前に方向性を決めておくと安心です。上にも書きましたが、病院や介護施設で亡くなった場合、その場で葬儀社を紹介されることがありますが、選択はあくまで自由です。急ぎの場面でも慌てず、希望や予算に合う会社を選びましょう。
お墓がある方は、菩提寺(お墓のあるお寺)にまず相談を。宗派の作法や僧侶の手配、お墓・納骨の流れに影響するため、連携できる葬儀社を選ぶことが大切です。
また自分の家の宗派がある場合や、親の希望がわかっていれば可能な限り取り入れます。
あとは複数社から事前見積もりを取り、サービス内容や対応範囲、追加料金の有無を確認することが大切です。地域や宗派によって対応力が異なる場合もあるため、条件を整理しておくことで、いざという時にスムーズに依頼できます。
喪服・数珠の準備
喪服は事前に試着してサイズを確認しましょう。50代になると体型の変化で、若い頃に購入した喪服が着られないケースも少なくありません。
数珠は略式で問題ない場合が多いですが、宗派によって作法や持ち方が異なるため、高齢の親族が多い場合は注意が必要です。
靴やバッグは黒一色で、光沢や装飾のないシンプルなものを選びます。これらを事前に揃えておくことで、急な場面でも慌てずに対応できます。
葬儀費用と支払い方法を考えておく
葬儀費用は現金払いが一般的でしたが、最近は振込やクレジットカードに対応する葬儀社も増えています。
僧侶を呼ぶ場合のお布施や戒名料は葬儀費用とは別途必要で、金額は寺院・地域・宗派によって大きく異なり、全国平均では総額15〜200万円と非常に幅があります。この費用は現金で用意します。
また、口座名義人が亡くなると預金は原則として凍結され、相続手続きが済むまではお金をおろせなくなるので注意が必要です。なお葬儀費用については金融機関によって相続手続き前に払出し可能な場合があります。
いざという時に慌てないためにも、支払い方法や必要額、預金の引き出し条件について事前に確認しておくことがおすすめです。